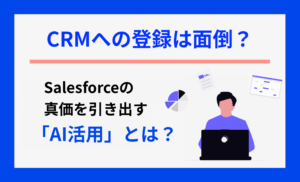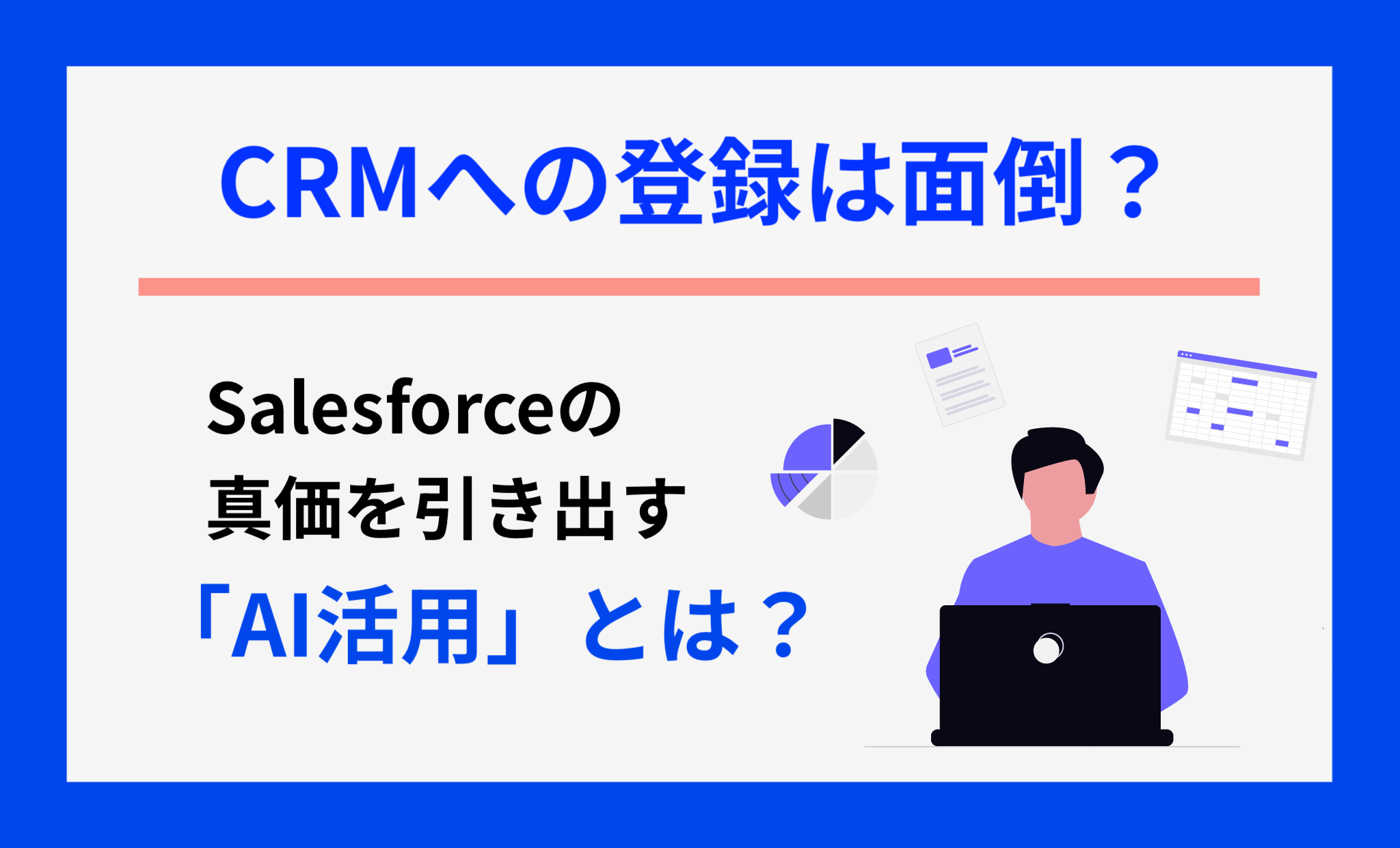プロフィットセンターという用語を聞いたことはあるでしょうか?組織運営や企業経営の話になると必ずといっていいほど聞かれるプロフィットセンターですが、どのような考え方なのかを正確に把握している方はそれほど多くはありません。また、同様の考え方にコストセンターというものもありますが、両者の違いをご存知ない方もいらっしゃるでしょう。そこで本記事では、プロフィットセンターとコストセンターの違いと、これらの組織形態が営業活動に与える効果について詳しく解説いたします。>【PDF無料ダウンロード】営業DX成功への近道! 失敗する原因と解決策をご紹介。

プロフィットセンターとは?コストセンターとの違い、組織における営業部門の役割を解説
オススメの資料
-

UPWARDで成果を出している企業の成功事例をご紹介
資料ダウンロードはこちら
目次
プロフィットセンターとコストセンターの違い
最初に、プロフィットセンターとは何か、そしてコストセンターとは何かについてご説明します。この考え方がすべての企業・組織に当てはまるわけではありませんが、業績を拡大させるにはこの2つの考え方は非常に重要な意味を持ちます。
プロフィットセンターとは
プロフィットという単語は、「利益」や「収益」という意味を持ちます。ビジネスにおいては、プロフィットセンターは「利益を生み出す部門」を指して使われる用語です。
企業の中で利益を生み出す部門というと、営業部門が真っ先に思い浮かぶ方は多いでしょう。実際は、営業企画部門やマーケティング部門、メーカーの製造部門、経営戦略部門などもプロフィットセンターに位置付けられることがあります。企業によっては、支店や営業所をプロフィットセンターと定義するケースもあるようです。
プロフィットセンターではその部門に関する収入と費用の両方が集計され、差額である利益を最大化するようにミッションが与えられます。なお、国内においては「事業部制」と呼ばれることもあります。
コストセンターとは
コストセンターとはプロフィットセンターと対になる概念で、会社にとって利益を生まず「コストとなる部門」を指します。具体的には、総務部や人事部、経理部などの間接部門など。研究施設や倉庫部門などもコストセンターに含まれることも多いようです。
コストセンターは、部門に係る費用を最小限に収めることをミッションとしています。
企業によって異なる捉え方
なお、このプロフィットセンターとコストセンターとの区別は企業によって異なります。一例として、製造部門をプロフィットセンターとした場合とコストセンターと位置付けた場合とで比較してみましょう。
プロフィットセンターと位置付けた場合、利益率の高い製品に注力するようになります。製造工程が複雑で製造コストがかかる製品であっても、大きな利益が見込めるならば積極的に対応します。
コストセンターと位置付けた場合は、製造コストに着目してみましょう。製造コストの高い製品は中止し、製造コストの安い製品に注力することになります。
また、同じ製品でもより安い原材料の調達を意識するのがコストセンターのミッションです。ただし、品質を落とすのではなく維持したままコストを抑える方法を考えるのが条件となります。
このように、特定の部門をコストセンターと位置付けるかプロフィットセンターと位置付けるかは、企業経営における認識の違いです。戦略次第でコストセンターをプロフィットセンターに変更できるため、柔軟に使い分ける必要があります。
>【PDF無料ダウンロード】営業DX成功への近道! 失敗する原因と解決策をご紹介。
プロフィットセンターとしての営業部門の役割
プロフィットセンターとコストセンターは企業によって認識が異なりますが、営業部門はほぼすべての企業がプロフィットセンターと位置付けていることでしょう。
営業はお金を稼いでくることを目的としています。しかし、単にお金を稼ぐだけでなく、稼ぐためのコストを精査し利益を最大化することが求められているのです。
極端な例ですが、1億円の商品を7000万円のコストをかけて販売するよりも、5000万円の商品を1000万円のコストをかけて販売する方がプロフィットセンターとして優秀です。ここでいうコストは営業部門の中だけでなく、製造原価やメンテナンスに係るコストも含めた会社全体でのコストとなります。
つまり、営業は会社全体のコスト構造を把握し、それを商品価格に転化した上で利益を最大にするような戦略が求められるのです。


プロフィットセンターは営業部門だけではない
営業部門だけでなく、カスタマーサービスやコールセンターもプロフィットセンター化し、利益拡大に貢献することができます。利益というのは何もお金だけでなく、製品やサービスへの評価やリピート率も立派な利益です。
その意味において、顧客対応によってサービスへの評価やサービス継続率に影響を与えるカスタマーサービスやコールセンターも、プロフィットセンターとして機能しなければならないといえます。
>【PDF無料ダウンロード】営業DX成功への近道! 失敗する原因と解決策をご紹介。
SFA/CRMを活用して部門間でデータを一元管理
営業部門を含め、カスタマーサービスやコールセンターもプロフィットセンターと位置付けた場合、顧客に関する会社全体のデータ管理を連携しなければそのミッションを完遂できません。そのためには、社内各部署でバラバラに管理していた顧客情報を、SFA/CRM(営業支援ツール/顧客管理システム)で一元管理する必要があるのです。
エクセルで顧客情報の管理を行っていた場合、各部門での情報共有は難しいです。SFA/CRMの導入で煩雑な顧客管理がスムーズに行えるようになれば、結果、利益増につながります。
このように、営業部門だけでなく、顧客と接するすべての部門がプロフィットセンターとして活動することが会社の利益を最大化する要因となるのです。
▽ 会社全体で営業活動データを管理/連携し、利益を最大化するイメージ
※「UPWARD」はさまざまなCRMとの連携が可能です。こちらはSalesforceと連携した場合の一例となっております。
営業管理の機能を備えるSFAツール「UPWARD」が5分でわかる
【無料】「UPWARDご紹介資料」を今すぐダウンロードする
関連記事>>CRM・SFAの違いは?機能や役割の違いからどちらを選ぶべきか解説
おわりに
プロフィットセンターとコストセンターはどちらが優れているかではなく、企業における戦略の違いによって位置付けられる概念です。現在では多くの企業が組織のプロフィットセンター化を進め、利益を最大化する方向に舵を切っています。
しかし、社内のデータ連携が十分でなければかえってビジネスチャンスを逃す結果につながりかねません。プロフィットセンター化を検討している企業の方は、SFA/CRMを活用した社内のデータ連携と一元化を積極的に検討すべきです。
世間にはさまざまなCRM/SFAツールが出ていますが、営業組織のデータ連携に特におすすめしたいのがUPWARDが提供する「UPWARD」です。
「UPWARD」は、営業マンの訪問や電話の活動を、ほぼ自動で標準化・定型化・定量化して記録することができます。
さらに、とことんシンプルさにこだわったUIで、ITが得意ではない営業マンにも使いやすいものとなっています。簡単にデータ入力ができる、レポートがわかりやすいなど、大手企業を中心とした約300社の導入企業から非常に好評なSFAツールとなっています。
ぜひ、「UPWARD」の導入と活用をご検討ください。
営業管理の機能を備えるSFAツール「UPWARD」が5分でわかる
【無料】「UPWARDご紹介資料」を今すぐダウンロードする