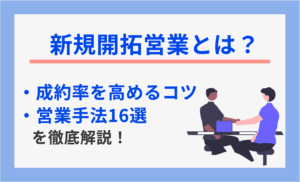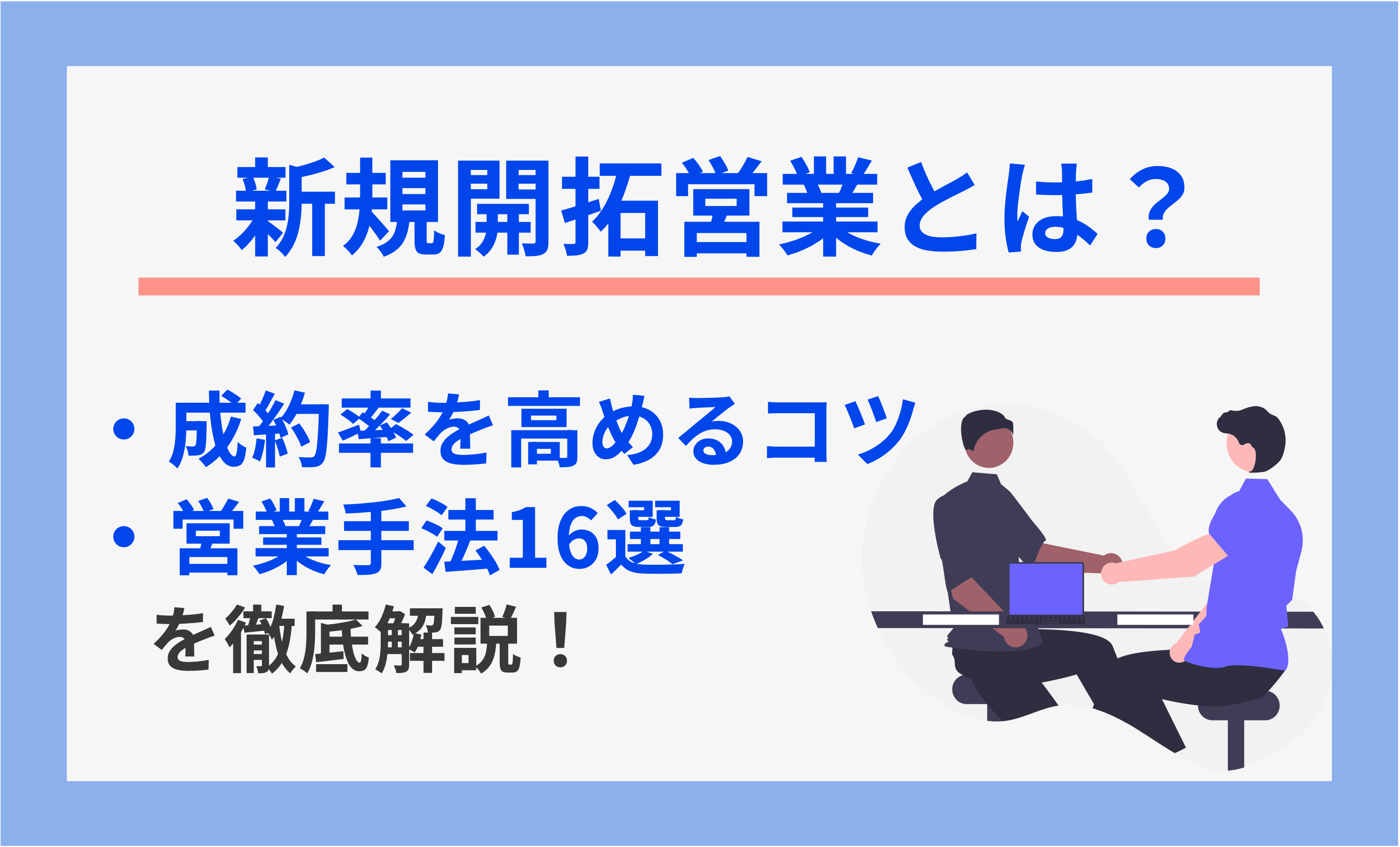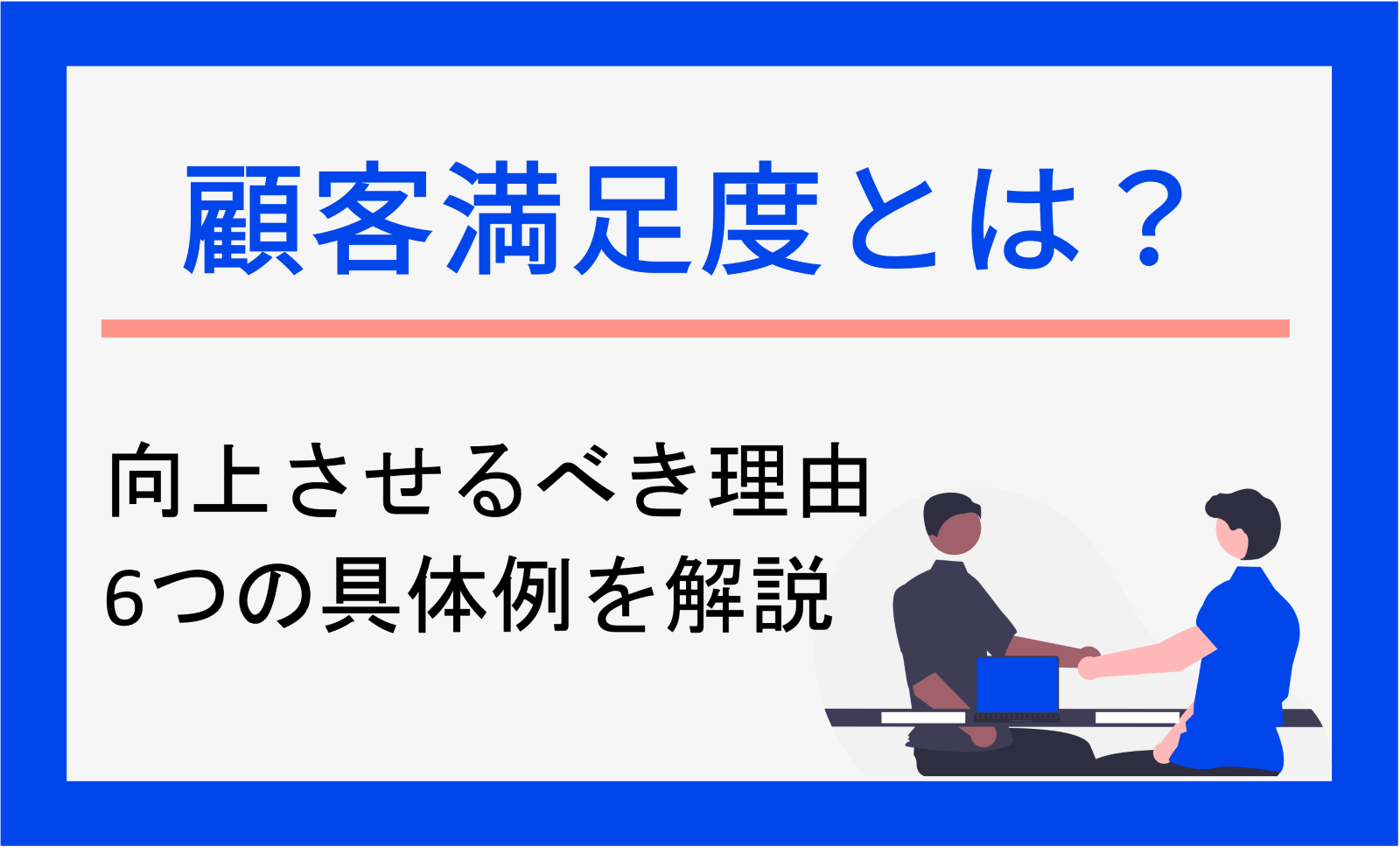「パイプライン管理」とは、初回のアポイント獲得から受注までの流れを可視化し、分析や改善を行っていくマネジメント手法を指します。パイプラインは、「営業活動の一連の流れ(業務フロー)」をパイプに見立て、案件がパイプの中を受注に向けて流れていく様子をイメージした表現です。本記事では、パイプライン管理とは具体的にどのような手法なのか、導入にはどんなメリットがあり、気をつけるべき点は何なのか、を解説していきます。

パイプライン管理とは?3つのメリット・手順・注意点を徹底解説!
オススメの資料
-

UPWARDで成果を出している企業の成功事例をご紹介
資料ダウンロードはこちら
目次
パイプライン管理とは
.jpeg)
パイプライン管理とは、初回のアポイント獲得から受注に至るまでの営業プロセスを可視化し、分析・管理する手法です。
営業パーソンが目標を達成し続けるために、目標やモチベーションを管理する営業マネジメント手法としても活用されます。
パイプラインは、石油や天然ガスなどを輸送するために設置する管路のことです。冒頭で紹介したように、「顧客との初回訪問から受注までの一連の流れ」がパイプの中を通っているように見立て、パイプライン管理と呼んでいます。
パイプラインの役割は、「営業プロセスの可視化」です。バラバラに管理している各営業プロセスをひとつの流れとして捉え、営業プロセスを定量的な指標に基づいて分析・管理することで、ボトルネックの発見や営業プロセスの中の無駄を見つけやすくします。それらを改善することで、営業活動全体の効率化を図れるようにするのです。
▼一般的な営業パイプラインの例:
テレアポ→初回訪問→ヒアリング→提案→見積もり→クロージング→受注
各プロセスが、数字で把握できる具体的な行動になっている点がポイントです。これによって、各営業担当者の主観に頼らず数字によって客観的に状況を把握できるようになります。
パイプライン管理が必要とされる背景
国をあげて働き方改革や生産性の向上、業務効率化が叫ばれているなか、営業活動においても、限られた営業時間のなかで売上目標を達成するために、無駄を無くし、営業活動の効率化をすることが求められています。
しかしながら、従来の営業活動では、営業個人の経験やスキルに頼っている部分も多く、どこに無駄があり、何から効率化したら良いか判断がつかないマネージャーも多いのではないでしょうか。
その結果、どこにボトルネックがあるか分からず、無駄が多い営業活動スタイルからなかなか抜け出せない営業組織も多いと聞きます。これらを解決するためには「パイプライン管理」を実施する必要性があります。
パイプライン管理を導入する3つのメリット

パイプライン管理を導入するメリットは3つあります。なぜ営業活動にパイプライン管理が導入されるのか。メリットを知れば納得していただけることでしょう。
課題の発見が速やかになる
パイプライン管理を実施することでは、勘や経験に頼らない、データに基づく組織運営が可能になります。
例えば、ある営業チームで売上目標の未達が続いていたとします。テレアポ・初回訪問・ヒアリング・提案など、各ステップをバラバラに分析する、また、自分のチームだけを分析しても、原因の特定に時間がかかることでしょう。
パイプライン管理によって目標が達成できている他のチームと比較をすることで、自チームの問題の原因を速やかに発見できるようになります。原因の発見が早まれば、それに対する打ち手も迅速に用意することができるでしょう。
チーム単位だけでなく、個人単位でも同様に、課題の特定がしやすくなります。営業個人への指導はとかく精神論に陥りがちですが、パイプライン管理をすれば、営業個人の活動プロセスにおける各数値と自身のKPIを比べることができます。客観的な数値に基づく形でボトルネックを把握できれば、生産的な指導を行いやすくなるでしょう。
営業目標・予算を論理的に算出できる
パイプライン管理によってデータを蓄積しておけば、各過程の歩留まりや受注率などを正確に把握できます。それらのデータを元にシミュレーションを行えば、可能な行動量から逆算して、四半期や年度ごとの適正な売上計画、ならびに営業目標を算出することが可能です。
反対に、営業目標からはじめて営業計画に落とし込んでいくこともできます。計画の際に「現状の延長線では営業目標を達成する行動量が担保できない」といった課題を発見することも可能なので、事前に業務改善や人員手当といった対策も準備しやすくなるでしょう。
マーケティングにも活かせる
顧客との初回接点を、広告やSEOといったマーケティング活動で獲得しているのであれば、チャネルごとにパイプラインを分析することで、それぞれの効果測定、ならびにどのチャネルに注力するのが最も成果に貢献できるのか容易に分析できます。
効果測定をする際は、初回接点で集客したリード(見込み客)が最終的な受注に結び付いていなければ、むしろ営業リソースの浪費につながってしまいます。そのため、受注までを含めてチャネルごとのパイプラインを分析することが、営業活動の効率化や生産性向上につながるでしょう。
パイプライン管理を行う手順
パイプライン管理のプロセスには、大きく分けて以下の4つのステップがあります。それぞれについて、詳しく説明いたします。
営業業務のフローを整理する
まず、営業業務のフローを整理することから始めます。ここでは、社内の営業活動をすべて把握し、それらを明確な手順やプロセスに落とし込んでいくことが重要です。
また、各営業業務のフローごとの目標を設定し、進捗状況を把握できるようにしておきましょう。
営業業務の課題を抽出する
次に、営業業務の課題を抽出します。フローの整理が終わったら、営業活動の中でどのような問題が発生しているのか、具体的に洗い出します。課題は、営業活動の効率化やコミュニケーションの改善など、さまざまな視点から捉えることができます。
課題ごとに改善案を立案
課題が明確になったら、課題ごとに改善案を立案します。改善策を立案する際には、営業メンバーや関係者から意見を集めることが大切です。また、他社の事例を参考にして、効果的な解決策を見つけ出すことも重要です。
継続的に分析・改善を行う
最後に、継続的に分析・改善を行います。改善策を実行した結果、どの程度の効果があったのかを定期的に分析し、状況に応じてさらなる改善を進めていくことが大切です。これにより、営業パフォーマンスを継続的に向上させることができます。

パイプライン管理を導入する際の3つの注意点

パイプライン管理はメリットだけではありません。活用の仕方によっては、導入の効果が薄れてしまいます。
パイプライン管理を効果的に活用するために、以下の注意点を頭に入れておいてください。
プロセスを細分化しすぎない
パイプライン管理でプロセスを細分化しすぎてしまうと、ミクロな部分に気を取られてしまい、本質的な課題の発見を遅らせてしまう可能性があります。
「データは細かく取れれば取れるほどよい」と考えてしまいがちですが、実務上は、どこに問題があるのか当たりがつけられるようになっていれば十分なケースがほとんどです。
そのため、パイプライン管理をするプロセスは、客観的で正確な全体像が確実に捉えられる粒度に留めておきましょう。
パイプラインは定期的に更新する
パイプラインを定期的に見直すことが大切です。
商談の進捗状況や市場環境、顧客のビジネス環境の変化に応じて、適切な対応を取る必要があります。定期的な見直しを行うことで、情報が常に最新の状態に保たれ、適切な戦略が立てられるようになります。
営業が入力を嫌がらないようにする
パイプライン分析で最も重要なのは、正確なデータが蓄積されることです。当然ですが、誤ったデータを元に正しい施策を立案するのはできません。ここで問題となるのがデータの入力作業です。
データ入力は各営業担当者が行うことがほとんどかと思いますが、「自分の成績に直接貢献しない無駄な作業」「自分の勤務時間を圧迫する作業時間」と捉えられてしまうと、入力が滞ってしまいます。また、そうなると活用できるデータを蓄積することができなくなってしまいます。パイプライン管理はチーム全体で行うべきタスクであり、それぞれのメンバーが持っている情報を共有することで、より効果的な商談が行えます。
この問題を解決するには、入力に手間がかからないようフォームを簡略化したり、今後の自身の営業活動に活かしたりできる環境作りが必要です。分かりやすいダッシュボードを設ける、入力する目的を営業組織内で目線を合わせるといった、営業が入力を嫌がらない環境づくりをしましょう。
集計・分析に手間がかからないようにする
パイプライン管理のメリットとして課題の発見が迅速化する点を挙げましたが、データの集計や分析に時間がかかってしまっては、せっかくのメリットが活かせません。
メールに書かれた営業日報をExcelに転記しているだとか、営業が手元に記録している内容を月次でまとめている…などの運用は非効率ですし、人件費の無駄にもつながります。
「営業が入力を嫌がらないようにする」ことにも役立ちますが、パイプライン管理を行うにあたってはSFAのような営業活動を管理できる専用ツールの導入をおすすめします。
SFAは営業活動を管理できる専用ツールとして、開発されているだけあって入力のしやすいインターフェイスが用意されていますし、入力されたデータは即時に反映され、そのまま集計・分析が可能です。とくに注視したい指標を、ダッシュボードにまとめて表示できる、といった機能を備えたツールもあります。
SFAを導入するメリットは、以下の記事で詳しく解説しています。SFAは営業活動の効率化を実現する機能が備わっているので、パイプライン管理の効果を高めるためにも、導入を検討してみてください。
パイプライン管理を成功させるためのおすすめ営業ツール
当社ではCRM・SFAの価値を最大化する営業DXツール「UPWARD」の提供および開発を行っています。

「UPWARD」を活用することで、スマホ一つで簡単にお客様のプロファイル情報、商談履歴、活動報告等の顧客データを半自動的にCRMへ蓄積します。
CRMへ顧客情報や営業活動の記録が蓄積されることで、営業活動における効率化できていない部分を見える化できるため、パイプライン管理にも適しています。
現場の担当者が営業日報や活動報告を作成する際は「UPWARD」上に自動で報告フォーマットが作成されるだけでなく、音声入力対応により、スキマ時間に簡単に報告が可能です。日々入力されるデータは地図上で可視化され、次に訪問すべき顧客が直感的に分かります。
より詳細な情報については下記URLからサービス資料をダウンロードいただけます。
「UPWARDご紹介資料」をダウンロードする
おわりに:パイプライン管理で定量的な分析や改善を実現
勘や経験に頼った営業マネジメントはもはや時代遅れです。もし、まだ定性的なマネジメントを行っているのであれば、営業活動における一連の業務フローを可視化して、定量的な分析や改善を実現するパイプライン管理の導入を検討してみてください。
さらにパイプライン管理の精度を高めるのであれば、SFAの導入も推奨します。
パイプライン管理を効率よく実施できる環境も必要なので、SFAの導入も選択肢に入れてみてはどうでしょう。