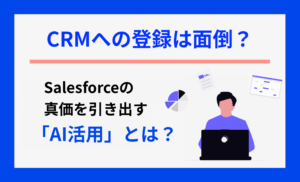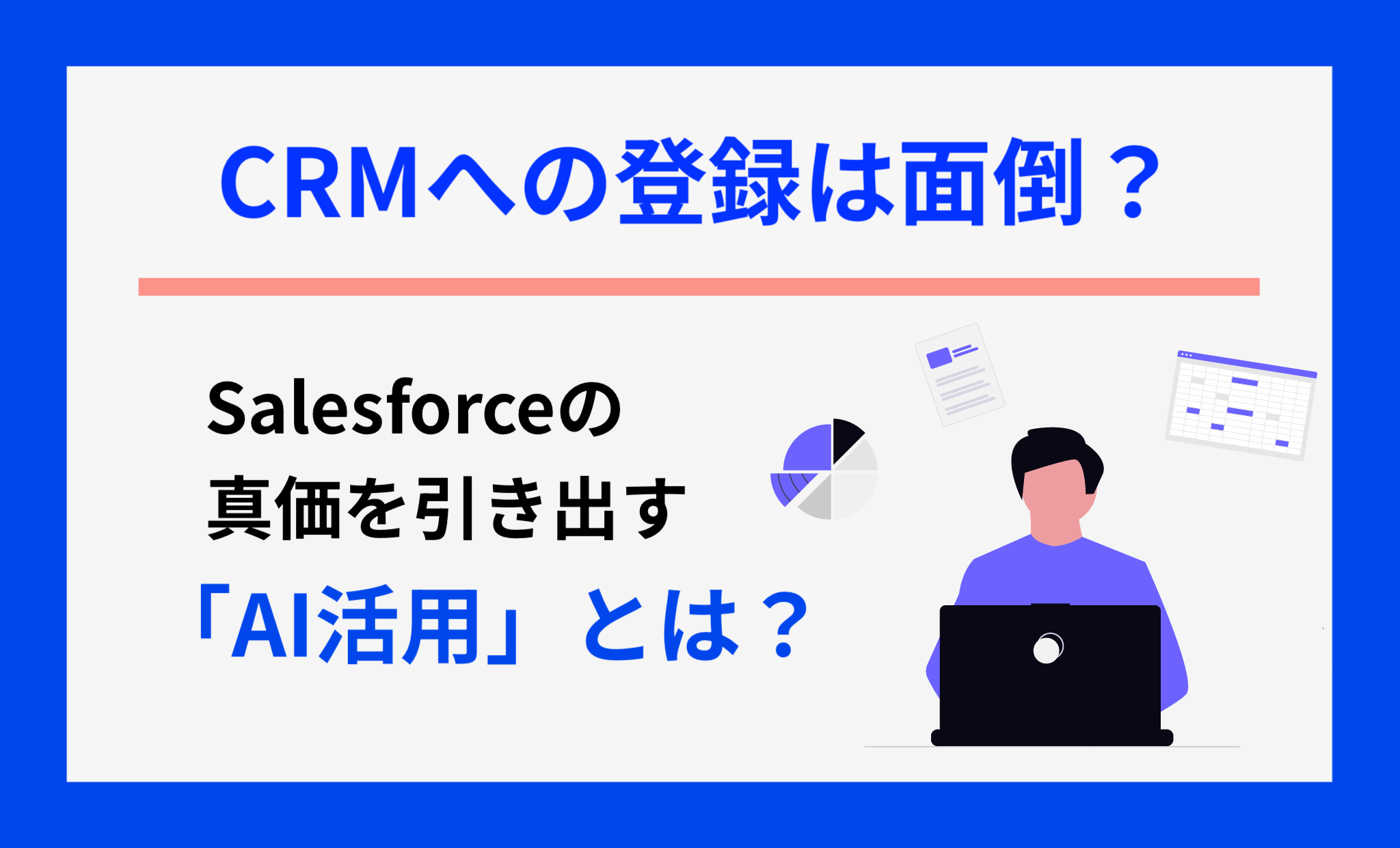コロナショックを経て、顧客とのコミュニケーション方法が変化し続ける営業組織。政府からも感染予防対策/働き方改革の一環としてオンラインとオフラインを組み合わせた“ハイブリッドワーク”が推進される中、営業現場には「顧客が見えない」「業績が上がらない」「成績が良い人、伸び悩む人の差が激しい」といった課題が増え始めています。 そんな中、営業担当者を支援する“セールスエンゲージメント”プラットフォームを開発・販売するUPWARD株式会社と、営業支援代行やコンサルティングといった、いわゆる“セールスイネーブルメント”を手掛ける株式会社セレブリックスとの対談を実施。 営業現場を見続けてきた2社が、変化する状況下でいかにして再現性のある営業組織へと導き、それぞれの現場担当者の創造性を引き出していくのか。エンゲージメント、イネーブルメントの両面から語ります。株式会社セレブリックス セールスカンパニー 執行役員 マーケティング本部長今井 晶也 (Imai Masaya)セールスエバンジェリストとして、セールスモデルの研究、開発、講演を行う。23年間におよぶ営業支援で蓄えた「売れるノウハウ」をもとに、法人営業のバイブルとなる顧客開拓メソッドを作成。2021年8月には本書の一般販売向けとなる書籍「Sales is 科学的に成果をコントロールする営業術」を扶桑社より出版。現在は執行役員 マーケティング本部長として、セレブリックスのコーポレートブランディング、事業企画、マーケティング、営業の統括責任者を兼任。UPWARD株式会社 代表取締役社長 CEO 金木 竜介(Kaneki Ryusuke)1973年東京都生まれ。LBS(位置情報サービス:location-based service)やGIS(地理情報システム:Geographic Information System)に精通し、これまでに200以上の関連システムを構築。国内初となるSalesforceと地図や位置情報を高度に連携させた、次世代型営業支援SaaS「UPWARD(アップワード)」を創業。現在、大手企業を中心に300社以上に導入されており、フィールドセールス向けのクラウドサービスとしては国内トップシェアを誇る。

【セレブリックス×UPWARD 後編】再現性のある営業組織へと導き、営業一人ひとりの創造性を引き出す
オススメの資料
-

UPWARDで成果を出している企業の成功事例をご紹介
資料ダウンロードはこちら
目次

金木:さて、前編ではお互いの取り組みについてと、営業担当者の魅力度を上げていくという共通の世界観について触れてきましたが、ここからはより具体的な組織としての再現性確保について伺っていきたいと思います。
今井さんから、コロナ禍で今までいかに“闇雲”な営業だったかを自覚し、これから変わっていこうとしている企業へ向けたアドバイスはありますか?

今井:そうですね…。私たちは普段勘やセンスに頼らずに「営業を科学する」ということを謳っているのですが、すべてが科学できるのかというと、なかなか難しい。1社1社悩みが異なりますし、変数が大きいので、「売れる」から紐解こうとすると上手くいきません。
ただ「この人から買いたくない」については、科学することができます。嫌がられない営業の型を作れば、真似ができます。初めて接点を持つ段階や、ヒアリング段階など一つ一つのプロセスごとに、お客様の「買いたくない」理由を解明していければ避けられるのではないかと。そういう面での再現性の追求はできるかな、と。ちなみにこの辺りを個々のマネージャーに任せてしまうと、個人の経験と知見に基づいたものになってしまうので、一度明文化しておく必要があります。
こうした失敗の原因を知っていくことが営業の型作りの第一歩なんですが、こういうことを話していると「営業の型なんて作ったら、創造性がなくなるんじゃないか?」と聞かれたりもします。結論、全く逆だと僕は考えています。

料理を作るときって、大抵レシピがありますよね。想いだけで美味しい料理が作れるかといったら、作れない。手順書が必要になります。そしてその手順書に則ってたくさん作っていくと、作り方や技術が手になじんできます。そこまで来てから、食べる人の好みや体調などに合わせたベストな料理を作ることが出来るようになります。
型を知っているからこそ、最後にアレンジをすることができる。そのアレンジの部分に、営業担当者の創造性が発揮されるのだと考えています。
金木さんは、セールスエンゲージメントにおいてはどんなところで創造性の大切さを提唱されていますか?

金木:僕らは「Go smarter, anywhere」をビジョンに掲げ、フィールドセールスの方々がどこでも快適に働けるようなスタイルを提供しています。僕らのお客様は、新規顧客の開拓もあれば既存顧客へのルート営業もある。外回りもあれば内勤もあって、カフェや車の中でも仕事をしています。
そんな方々にどうすれば創造性を発揮してもらえるか、その答えが僕らは“自動化”にあると思っています。創造性を阻むような作業と呼ばれるもの、顧客接点における情報共有や活動報告などを全部自動化してデジタライズして、分析可能な定量データに変換する。
これは野球のスコアと一緒で、打率や得意球種が見えれば自ずと自分の戦い方も見えてくる。まずはとにかく打席に立って、自分だけのスコアを溜めていく。データが溜まってくると傾向が見えてくるので、以前訪問で商談がフェーズアップしたお客様と似たような企業が近くにあったら位置情報をもとにお知らせして、勝率の高いアプローチ先をレコメンデーションしていく。
理想は、フィールドセールスが何も作業に追われていないまま、次の再現性を迎えていくことですね。



今井:創造的な発想やアイデアを作るのに、営業パーソンとしてのゆとりや余白って大切ですよね。分刻みの仕事をしていると、左から右へ、1社1社への提案に対する創造性はどんどん失われていく。
金木さんが仰った通り、本当に人がやらなくても良いところを自動化してあげれば、豊かな発想が生まれてくるようになると思いますね。
特に新規開拓営業なんかは、基本的にはほとんどが失注に向かっていると思っています。プッシュ型の営業をかける際は特に、クリエイティブでクリティカルな新しい発想を示せなければ、当たり前に「今まで必要としていなかったからいらない」と言われてしまう。お客様の前提を覆す必要があるんです。
お客様になかった発想を与えていく、新しい世界を見せていくためには、ゆとり、創造性が必要。そこに時間をかけるためにも、余計なところでつまづかせない。そう言った意味ではセールスイネーブルメントもセールスエンゲージメントも、両方大事だなと感じました。

金木:そうですね。色々お話ししてきましたが、セールスエンゲージメントとセールスイネーブルメント、やはり今、どちらも求められているソリューションなんだろうなと思います。

今井:どこもかしこも人がやってきた時代は終わりつつあって、営業力のあった世代が辞めてみんなあたふたしだしているな、と感じます。問い合わせや反響はすごく増えていますね。
いずれにしても、目的と手段の関係で、どちらもあくまで手段として捉えていただくことが重要ですよね。企業として「こうなりたい」という目的を持って、そのためには誰がやっても成果が出せるような仕組みやシステムを導入しなきゃいけないよね、というように考えていただきたい。


金木:再現性のある営業組織が出来ている会社があまりないのは、営業としてどう成果を出すかという目標や定義、引いては会社のビジョン、ミッションを再構築するというところから始めないと、作りにくいからでしょうね。
ストーリーから手をつけないと、結局は手段の選定まで適切ではなくなっていきます。人間の「個」に対して理解を深めていって、共感を得られないと、再現性というのはなかなか難しいなと感じます。
今回のキーワードだった、セールスイネーブルメントとセールスエンゲージメント、営業の再現性と創造性は、やはりどちらが先か後かという話ではなく、相互に意識しながら繋げていかなくてはいけないものですね。

今井:難しいな、とは思いますが、結局中心に添えるべきは“お客様”。お客様が「気持ちよく買う」。だから、営業の再現性が必要。そして営業パーソンの創造性が上がれば提案の質も上がり、お客様の購買体験が良くなる。
そのためには、顧客体験のどこにボトルネックがあるのか。営業パーソンのエンゲージメントなのか、イネーブルメントという形で仕組み作りが優先なのか、顧客軸で探っていくと、有効なメスになるのかな、と。テクノロジーを入れる、教育をする、はあくまで手段になります。お客様の購買体験向上を軸とした目的を定めて、どこから着手していくのかを考えていくのが大事かなと思います。

金木:お客様と向き合って、詰めていかなくてはいけませんね。つまりは、営業組織の再現性を向上させるためにも、営業パーソンの創造性を高めていくためにも、まず最も必要なことは「お客様の解像度を上げる」ということですね。
今井さん、本日は貴重なお話、ありがとうございました。